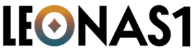立ち仕事で足が疲れたときは?すぐできる解消法を紹介

長時間同じ姿勢でいると、血行が悪くなるため、特に下半身へ疲労がたまりやすいものです。痛みやむくみ、だるさを感じて、辛い思いをしている方もいるでしょう。
そこで今回は、立ち仕事で疲れた足をリフレッシュさせる方法をご紹介します。少しでも疲れを和らげたい方は、ぜひ参考にしてください。
立ち仕事で足の疲れが生じる原因
立ち仕事により足の疲れが生じるのは、いくつかの原因があります。まずは、主な理由について解説しましょう。
ポンプ機能がうまく働いていないから
ふくらはぎには、「ヒラメ筋」という大きな筋肉があります。この筋肉は、下半身の血液をポンプのように押し出し、心臓に血液を戻す役割を担っています。
ふくらはぎの血行が悪化し、ポンプ機能が働かなくなると、足にたまった血液がうまく戻りません。結果として、下半身の老廃物が排出されなくなり、むくみやだるさが起こります。
立ち姿勢がよくないから
姿勢が悪いと、筋肉や関節に余計な負荷をかけます。たとえば、片足に体重をかける立ち方は体の一部に過剰な負荷をかける原因に。やがて筋肉が疲労して老廃物がたまりやすくなり、だるさや痛みが発生します。
また、体にはバランスをとろうとする機能が備わっています。体の片側だけに重さがかかる状態が続くと、骨盤や背骨のバランスが崩れ、痛みが起こることも。足だけでなく全身の不調につながる可能性があるため、注意が必要です。
体に合わない靴だから
靴には、歩行時の衝撃を吸収し、体への負担を和らげる役割があります。クッション性の低いものや、足の形に合わないものを履いていると、筋肉や関節へ大きな負荷が加わることも。そのまま履き続けると、体に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、足は全身の重さを支えているため、立っているだけでも大きな負荷がかかっています。靴が体に合っていないと姿勢も悪くなり、膝や腰など全身の痛みにつながることも。体の疲れやダルさが起きやすい時は、靴を見直してみるとよいでしょう。
職場の床に原因があるから
床が原因で、疲労につながる可能性もあります。たとえば、オフィスビルでよく見かけるコンクリートやタイルの床は硬いため、大きな衝撃が体に伝わります。結果として、足裏や膝が痛くなったり、腰に負担がかかってしまったりすることがあるでしょう。
一方で、柔らかすぎる床が悪影響を及ぼすこともあります。柔らかい床の上では、バランスを保つため普段使わない筋肉をたくさん使わなければいけません。そのため、かえって疲れを感じやすくなるケースがあります。
床の硬さや柔らかさは、私たちの足の健康に大きな影響を与えます。床の素材を変えるのは難しいため、クッション性の高い靴を履いたり、フローリングの硬さを和らげるマットや絨毯を敷いたりして対策するとよいでしょう。
足の疲れが生じた時の対処法
立ち仕事で足の疲れが生じた時は、早めに対処するのが重要です。ここからは、すぐに実践できる方法をご紹介します。
こまめに歩く
立ち仕事による疲れを軽減するためには、同じ場所で立ち続けるよりも、こまめに歩くのが有効です。歩行によってふくらはぎの筋肉が収縮し、血流が促進されるため、むくみやだるさが和らぎます。
また、筋肉や関節を適度に動かすことで血流を促し、疲労の蓄積を予防します。立ち姿勢が続いたときは、短時間でも歩くのがおすすめです。
その場を離れるのが難しい時は、その場で足踏みをするだけでも効果があります。背筋を伸ばして肩幅まで足を開いたら、左右交互に足踏みをしましょう。両腕を大きく振りながらやれば全身運動にもなり、さらに効果を高められます。
蹲踞(そんきょ)のポーズをとる
蹲踞とは、うずくまったり、しゃがんだりするポーズのこと。相撲や剣道などで見られる、日本の伝統的な姿勢の一つです。
深く腰を落としたら、かかとを浮かせ、背筋をしっかりと伸ばすのがポイントです。足の疲れを感じたときにこの姿勢を取ると、ふくらはぎや太ももの筋肉をゆるめられます。
また、蹲踞にはバランス感覚を鍛える効果もあります。つい背中が丸まってしまったり、片足に重さをかけたりしがちな方は、積極的に取り入れるとよいでしょう。
アキレス腱のばしや足首回し
ストレッチには筋肉の緊張を和らげ、血流を促す効果があります。立ち仕事は長時間同じ姿勢が続くため、筋肉のこわばりを招きます。定期的にほぐして、柔らかさを維持するのが重要です。
気軽にできるストレッチには、アキレス腱のばしや足首回しなどがあります。血行が促されるため、だるさやむくみが気になったタイミングで実践してみましょう。
横になって足を高く上げる
休憩室にベッドやソファなどがある場合は、足を心臓よりも高く上げながら横になるのもおすすめです。下半身にたまった血液を効率よく心臓に戻すことができ、むくみや疲労感の解消につながります。
仰向けに寝たら、高さ10cmほどのクッションに足をのせます。クッションが高すぎたり長時間やり過ぎたりすると、腰に負担をかけてしまうので注意しましょう。
ふくらはぎをマッサージする
ふくらはぎの筋肉を柔らかくし、ポンプ機能の回復を促すのも有効です。ふくらはぎをさすり上げたり、優しくトントンと叩いたりするだけでも効果があります。
ただし、マッサージのときに力を入れすぎるのは逆効果です。筋肉が硬直してしまい、血流が悪くなる原因になります。心地よさを感じる程度の力を心がけましょう。
立ち仕事による足の疲れの予防法
立ち仕事が毎日ある方は、疲れやだるさが起きないように、あらかじめ予防するのも大切です。ここでは、簡単にできる対策を順番にご紹介しましょう。
靴やインソールにこだわる
立ち仕事では、地面からの衝撃を軽減できる靴やインソールを使用するのがおすすめです。たとえば、クッション性の高い靴を履いたりアーチサポート付きインソールを入れたりすると、足裏にかかる負荷を分散できます。
また、足の形に合った靴を選ぶのも重要です。合わない靴を履いていると、歩行バランスを崩したり、ひざや足首に負担をかけたりするためです。メーカーによって靴のサイズや形は異なるため、実際に履いてみてから、フィットするものを選びましょう。
また、靴が滑りやすいと余計な負荷が筋肉や関節にかかるため、滑りにくいものを選ぶのも重要です。摩擦力の高いラバーソールを使っているものや、凹凸がしっかりついたものを選ぶとよいでしょう。
靴下を変える
むくみが気になる方は、靴下を変えるのも効果的です。履くだけで簡単にむくみ対策ができるため、運動やストレッチをする時間がとれない方にもぴったりです。
たとえば、ふくらはぎのだるさが気になる場合、足首から太ももにかけて適度な圧力がかかる着圧ソックスが適しています。圧力によって血流がうながされ、むくみやだるさが軽減します。足全体がだるいときは、つま先からお腹までカバーするストッキングタイプもおすすめです。
ただし、圧力が強すぎたりサイズが合っていなかったりすると、かえって締め付けが辛くなることもあるので注意が必要です。むくみが辛すぎる場合は、ゆったりとした靴下の方が過ごしやすいこともあるため、試し履きをしてから取り入れるようにしてください。
体を冷やさないようにする
体が冷えると血流が滞り、老廃物が蓄積されやすくなります。また、体温が低下すると代謝も悪くなるため、疲れやだるさなどが起きる原因に。冷房のきいた室内や、寒い時期に屋外で立ち仕事をされている方は、特に注意してください。
体の中でも、つま先や足首は血流が滞りやすい箇所です。レッグウォーマーを履いたり、専用のカイロを貼ったりして、冷えを予防しましょう。
日頃からしっかり湯船につかる
シャワーだけで済ませることが多く、湯船につかる時間がない、という方も多いもの。しかし、立ち仕事で辛い時こそ、しっかりと入浴する習慣をつけてください。
入浴には体をリラックスさせるほか、手や足の血行を促したり、筋肉を柔らかくしたりする効果があります。15~20分程度の時間をとって湯船につかると、ふくらはぎや太ももに溜まった疲労物質が流れやすくなり、むくみやだるさを和らげます。
お湯の温度を38~40度くらいに設定するのもポイントです。42度以上の熱い湯に入ると交感神経が活発になってしまい、眠りを妨げてしまうからです。少しぬるいと感じるくらいの温度で、ゆったりとした気持ちで入浴しましょう。
入浴中にマッサージを行う
湯船につかっている時にマッサージをすると、血液の循環がさらに促進され、筋肉にたまった疲労物質が排出されやすくなります。特にふくらはぎや足裏を重点的に揉みほぐすと、筋肉のこわばりが和らぎます。
余裕がある時は、シャワーの水圧を利用してマッサージをするのもおすすめ。シャワーヘッドを足裏に当てて、ふくらはぎ・太ももの順番に押し上げていきましょう。温水と冷水を交互に当てると、血流がさらに促進され、むくみが解消しやすくなります。
まとめ
立ち仕事で足が疲れたときには、適切なケアが重要です。こまめに歩いたり、ストレッチをしたりして、だるさや痛みを長引かせないようにしましょう。
LEONAS1では、タイの伝統的なマッサージであるジャップカサイを提供しています。男性特有のお悩みだけでなく、足の疲れをはじめとした心身のコンディションの向上にも取り組んでいます。疲労やだるさがとれずにお悩みの方は、お気軽にご相談ください。